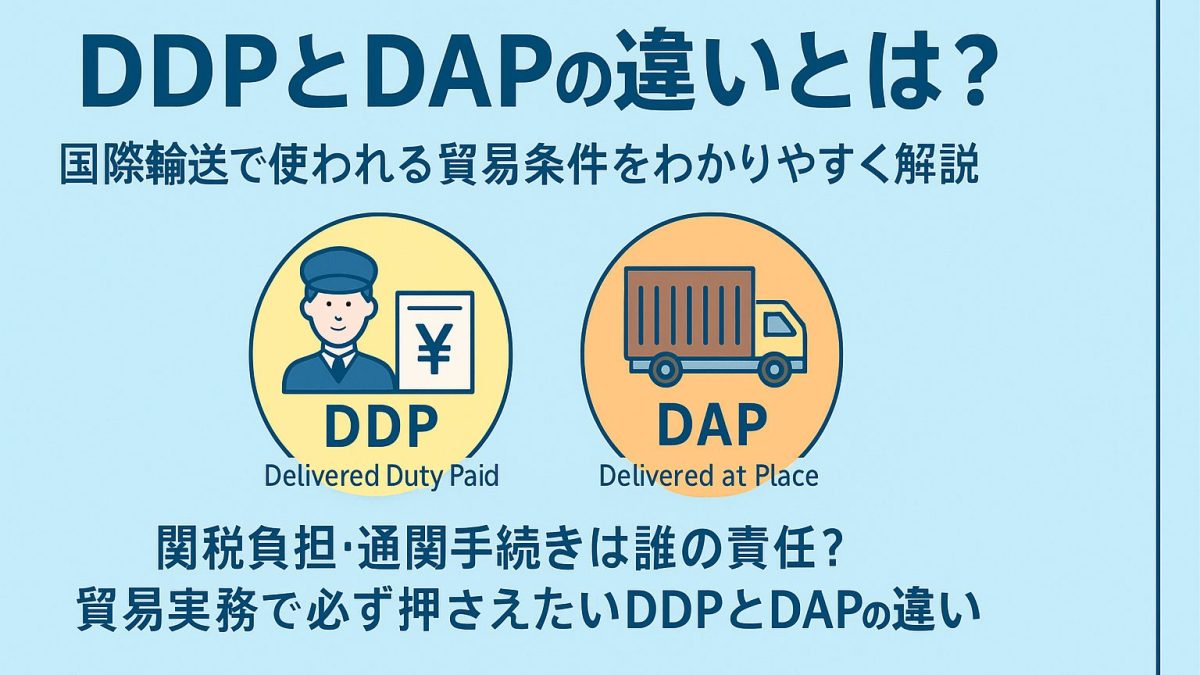国際取引の現場では、「DDP」や「DAP」などの貿易条件(インコタームズ)が頻繁に登場します。これらは貨物の引渡し場所や費用負担の範囲を定める重要な取り決めであり、誤解するとトラブルや追加コストの原因になります。
本記事では、特に混同されやすいDDP(Delivered Duty Paid)とDAP(Delivered at Place)の違いについて、図解や事例を交えてわかりやすく解説します。
目次
1. インコタームズとは?
インコタームズ(Incoterms)は、国際商業会議所(ICC)が定める貿易条件の国際的ルールです。輸出者と輸入者が「どこまで運ぶのか?」「どちらが費用を負担するのか?」などを明確にする目的で使われます。
現在の最新版は「インコタームズ2020」です。
2. DDPとDAPの基本定義
| 項目 | DDP(Delivered Duty Paid) | DAP(Delivered at Place) |
|---|---|---|
| 日本語訳 | 関税込持込渡し | 指定場所持込渡し(関税未払い) |
| 引渡し場所 | 輸入者の指定場所 | 輸入者の指定場所 |
| 関税・輸入消費税の支払 | 売主が負担 | 買主が負担 |
| 通関手続(輸入) | 売主が対応 | 買主が対応(ただし売主も支援する場合あり) |
3. DDPの特徴と注意点
✅ 特徴
- 売主が最も多くの責任とリスクを負う条件。
- 輸入国での関税・税金・通関手続きも売主が対応する。
- 輸入国に通関知識や登録番号(EORI番号など)が必要なケースも。
⚠ 注意点
- 売主が輸入国の制度を正しく理解していないと、貨物が滞留するリスクあり。
- 現地での通関対応にパートナー(通関業者、税関事務管理人)が必要。
- 越境ECや国際宅配でよく使われるが、事前確認が不可欠。
4. DAPの特徴と注意点
✅ 特徴
- 売主は貨物を買主の指定場所まで輸送するが、関税や通関手続きは買主が対応。
- 買主が輸入国の通関手続に慣れている場合に適している。
⚠ 注意点
- 買主が通関対応に不慣れだと、遅延や追加コストのリスクあり。
- 通関書類が正確でなければ通関不可となる場合がある。
5. よくある誤解と実務アドバイス
| 誤解 | 実際は… |
|---|---|
| DDPであればどんな国でも通関できる | 売主に現地通関資格がないと実務上不可能なケースあり |
| DAPは売主にすべて任せられる | 関税・通関対応は買主がやらなければならない |
| 越境ECならDDPが安心 | 小規模なセラーではDDPに対応できないことがある |
6. DDPとDAPの選び方のポイント
| 条件 | おすすめ条件 |
|---|---|
| 売主が輸入国での通関に対応できる体制がある | DDP |
| 買主が通関や関税対応に慣れている | DAP |
| 双方が初心者でトラブルを避けたい | CIF+現地通関業者の活用など別条件を検討 |
まとめ
**DDPとDAPの違いは「関税・輸入通関手続きの責任が誰にあるか」**という点に集約されます。
どちらを選ぶかは、双方の通関対応力やリスク許容度によって決まります。
貿易条件は契約の根幹に関わるため、インコタームズの理解と実務体制の整備が極めて重要です。
✅ この記事のポイントまとめ
- DDP:売主が関税・通関含めて全責任を負う
- DAP:売主は運ぶだけ、関税・通関は買主が対応
- 実務では、通関対応力・コスト・トラブル時の責任範囲を明確にして選択を!